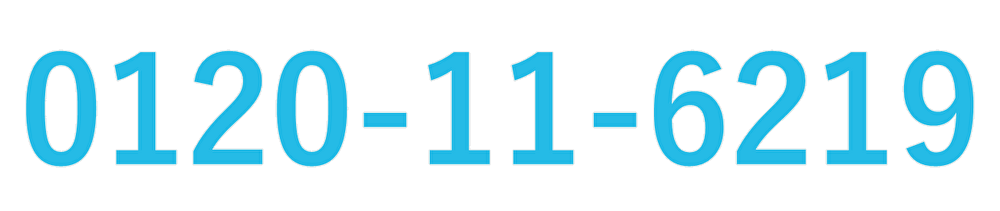-
公開日:
-
更新日:
梅雨に訪問介護で起こりがちなトラブルとは?気を付けたいポイントを紹介
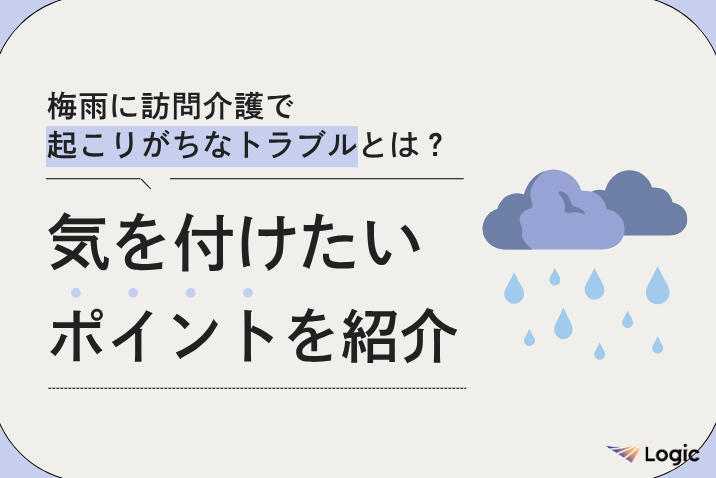
ジメジメとした日が続く梅雨の季節は、訪問介護の現場で働くヘルパーにとって、普段以上に気を遣う場面が増える時期です。
雨の中の移動や利用者の体調管理、湿気による衛生問題などが原因で、思わぬトラブルや事故につながることもあるでしょう。
本記事では、そんな梅雨の時期に、訪問介護で起こりがちなトラブルを具体的に挙げ、その対処法と未然に防ぐためのポイントを詳しく解説します。 日々の業務を安全にすすめるためにも、本記事を参考にしていただければ幸いです。
目次
梅雨の季節が、訪問介護に与える影響
利用者の自宅でのケアが中心となる訪問介護では、梅雨の時期は特に天候の影響を大きく受けます。
なぜなら、ヘルパーの移動手段や訪問先である利用者の自宅の環境が、雨や高い湿度によって影響を受けるためです。
例えば、雨の日は視界が悪く路面も滑りやすいため、移動時の転倒リスクが高まります。
そのため、自転車やバイク移動は危険が増し、公共交通機関も遅延することもあるでしょう。
また、雨に濡れたままの体でケアを提供せざるを得ないこともあり、ヘルパー自身が体調を崩しやすくなることも考えられます。
長引く高湿度はカビやダニの発生を招き、利用者の自宅の生活環境を悪化させ、健康や快適さを損なうことがあります。
このように、梅雨特有の天候は、サービス提供全体に影響するため、現場では細心の注意と対策が必要です。
梅雨に起こりやすいトラブル一覧紹介
梅雨の時期、訪問介護の現場ではさまざまなトラブルが起こりやすくなります。
ここでは、梅雨の時期に起こりやすいトラブルについて6つ紹介します。
移動トラブル
雨の日の自転車やバイクでの移動は危険度が増し、トラブルが起きやすくなります。濡れた路面、特にマンホールや白線は滑りやすく、ブレーキも効きにくくなるため注意が必要です。
また、雨粒で視界が悪化し、歩行者や障害物の発見が遅れることもあり注意が必要です。
雨に濡れて体が冷えると、体調不良や集中力の低下を招き、とっさの判断ミスにも繋がりかねません。
これらの要因が重なり、移動中の事故リスクが高まります。

玄関先・室内での転倒事故
ヘルパーが雨で濡れた傘や衣類、靴などから持ち込む水分や湿気で、利用者の自宅の玄関や床が滑りやすくなり、転倒事故の危険性が高くなります。 筋力やバランス能力が低下している高齢の利用者は、わずかな床の濡れでも足を滑らせ、骨折のような大怪我に至る事故も発生しています。ヘルパー自身も、急いでいたり荷物を持っていたりすると足元への注意が疎かになりがちです。濡れた靴で室内を歩き、滑る箇所を広げないよう注意が必要です。
衛生面の問題
梅雨の高温多湿な環境は、カビや細菌、ダニの温床で、アレルギーや喘息を悪化させる原因となります。特に浴室やキッチン、寝具等は注意が必要です。 気温と湿度の上昇は食中毒のリスクも高めます。
抵抗力の低い利用者が発症すると重症化しやすいため、食品管理は徹底しましょう。
また、汗や湿気によるあせも、おむつかぶれ、水虫のような皮膚トラブルも発生・悪化しやすくなるため注意が必要です。
気温や湿度の上昇による室内環境の悪化
梅雨の時期は湿度が高く汗が乾きにくくなるため、体内に熱がこもり熱中症を引き起こす危険が高まります。梅雨時はまだ身体が暑さに慣れていない方も多く、気温が低い日でも油断はできません。
特に高齢者は体温調節機能や喉の渇きを感じる機能が低下していることが多く、自覚がないまま熱中症や脱水が進行するケースもあります。 室内が蒸し暑く換気が不十分だとさらにリスクが高まるため、室温・湿度管理と水分補給の声かけが重要になります。
利用者の体調悪化
梅雨の気圧変動や高い湿度は、利用者の持病を悪化させることがあります。 よくあるのは、関節痛やリウマチの痛みが増したり、喘息発作が起きやすくなったりするケースです。 気圧の変動による頭痛やだるさを訴える方もいます。また、雨が続いて外出機会が減ると、活動量が低下し、気分が落ち込むなど心身の不調に繋がる場合もあります。
利用者の状態をよく観察し、普段との様子の違いに注意しながら、適切なケアを心がけましょう。
天候不良による急なキャンセル・予定変更
大雨や台風など著しい悪天候時には、利用者とヘルパーの安全確保のため、訪問サービスが急遽キャンセルや時間変更になることがあります。 これは利用者側から申し出る場合や、事業所判断の場合もあります。こうした変更は、ヘルパーのスケジュールや収入、利用者の生活(特に医療的ケアが必要な方や一人暮らしの方)に大きな影響を与え、双方にとって負担となり得ます。 悪天候時の対応について、事前の取り決めや連絡体制の確認が重要です。
トラブルを防ぐためにできること
梅雨特有の訪問介護トラブルも、事前の対策で予防可能なものも多いです。
ここでは、ヘルパー個人だけでなく、事業所全体で取り組むべき具体的な5つの対策を紹介します。
これらの対策を実践し、梅雨の時期も安全・安心なケア提供を目指しましょう。
事前の情報共有と柔軟なシフト調整
梅雨時のトラブル防止には、まず天気予報を確認し、早めの対策を心がけることが基本です。利用者宅への交通状況やヘルパー自身の状況など、変化する情報を事業所やケアマネジャーと共有できるとよいでしょう。
具体的には、状況に応じた訪問時間の調整や、代わりのヘルパーとの連携といった柔軟なシフト調整などが挙げられます。
介護ソフトのようなツールを活用すれば、リアルタイムな情報共有や急なスケジュール変更もスムーズに行え、天候による予定変更を最小限に抑えられます。
移動手段やルートの見直し
雨の日の移動は、普段以上に慎重になる必要があります。事前に訪問ルートを確認し、冠水しやすい場所や滑りやすい道などを避ける迂回路を検討しておくとよいでしょう。
また、移動には時間がかかることを見越して、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
自転車やバイクの場合は、滑りやすいマンホールや白線を避け、急ブレーキ・急ハンドルをしないよう注意が必要です。
大雨や雷のような悪天候の場合は、無理せず事業所に連絡し、指示を仰ぐ必要があります。
雨の日用の装備・着替えの準備
雨天の訪問には適切な装備が不可欠です。体が濡れると体調不良の原因にもなるため、以下のような防水性・透湿性に優れたものを選びます。
- 上下セパレートのレインウェア
- 滑りにくい靴底の長靴・防水シューズ
- 替えの靴下
- タオル
- 着替え一式
記録物やスマートフォンも防水バッグなどで保護できるとよいでしょう。

訪問先に濡れたまま上がらないよう、玄関先で水滴を拭う配慮も大切です。
室内環境のチェックと助言
訪問時には利用者の自宅の室内環境も確認する必要があります。- 湿度が高すぎないか(目安50~60%)
- カビが発生しやすい場所はないか
必要に応じて、利用者や家族に、換気や除湿機の使用、エアコンのドライ運転などを具体的に助言します。
熱中症予防のため室温にも配慮し、こまめな水分補給も促しましょう。
床が濡れていれば吸水マットを提案するなど、転倒防止にも目を配ります。
衛生管理
梅雨時期は特に衛生管理への意識を高めましょう。 食中毒予防のため、食材は適切に保存し、調理時は十分に加熱、調理器具も清潔に保ちます。 作り置きは極力避け、早めに消費する心がけが必要です。おむつ交換はこまめに行い、清拭で皮膚状態をよく観察します。 衣類や寝具が湿っていれば交換を促し、乾燥を保つことも重要です。 ヘルパー自身のこまめな手洗い・手指消毒も徹底しましょう。
参考:介護求人ラボ(https://kaigo-labo.com/news_343.html)/あなぶきの介護(https://www.a-living.jp/contents/2562/)/茨城県(https://x.gd/UWUSY/ 介護求人ナビ(https://www.kaigo-kyuujin.com/oyakudachi/break/44295)/前橋市(https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kenko/kenkozoshin/oshirase/35456.html)/ 東京都アレルギー情報navi.(https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/allergy/measure/indoor.html)
まとめ
梅雨時期の訪問介護は、移動の困難さや利用者の体調変化、衛生管理など、ヘルパーにとって気を遣う場面が絶えません。
しかし、これらのトラブルの多くは、事前の情報共有や適切な準備・対策によって予防したり、影響を最小限に抑えたりすることが可能です。 日々の記録や利用者情報の共有、急なスケジュール変更への対応を効率化する介護ソフトの活用も視野に入れ、事業所全体で梅雨に負けない安心のケア提供を目指しましょう。
介護ソフトCare-wingは、訪問の記録やシフト作成を通し、情報共有の円滑化や業務効率化をサポートしており、3,000を超える介護事業所に導入されています。
チーム内の情報共有や業務効率化に興味のある方は、以下の資料をぜひチェックしてみてください。
<ライター> 織田さとる
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。