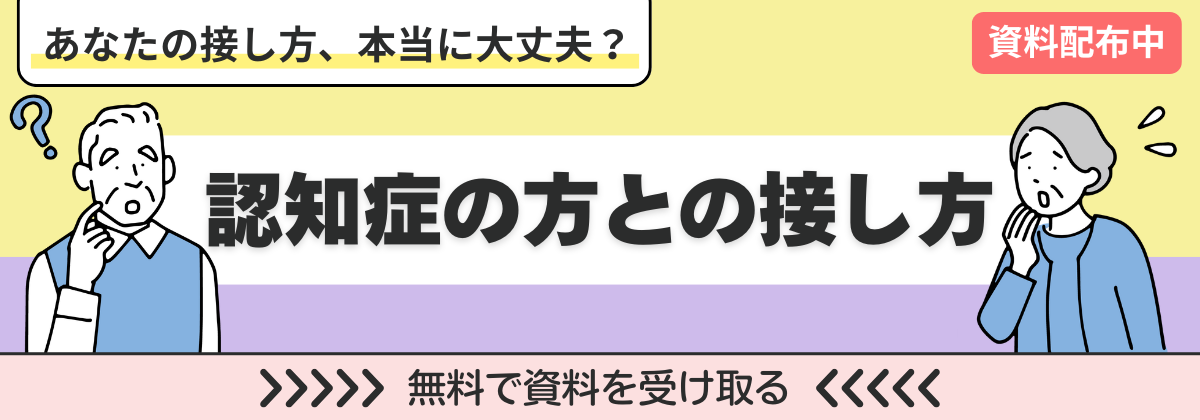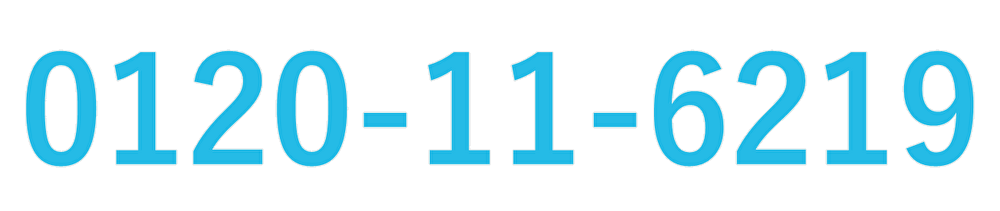-
公開日:
-
更新日:
認知症の利用者との接し方のポイントや注意点
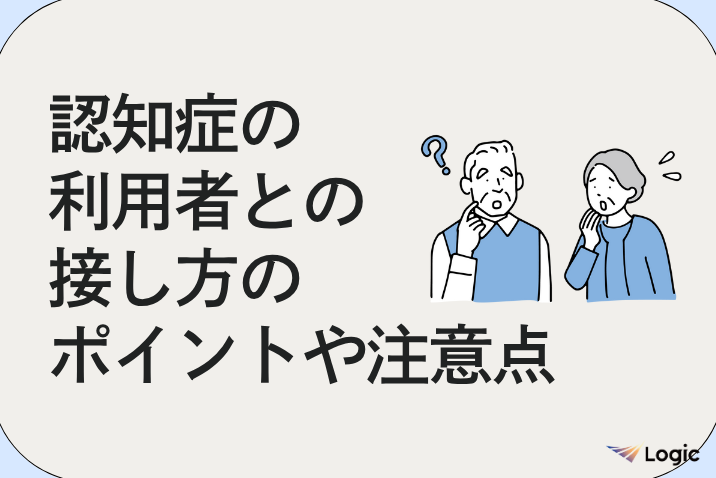
訪問介護の現場では、さまざまな状況への対応が求められます。 なかでも、認知症のある利用者とのコミュニケーションは、多くの職員が難しさや不安を感じる場面のひとつではないでしょうか。
認知症は、脳の機能の変化によって記憶や判断力が低下する病気です。 同じことを何度も言ったり徘徊したりするため、一見すると不可解に思える言動が見られることもありますが、その裏には本人なりの理由や不安が隠されています。
本記事では、認知症の方への接し方の基本原則から、現場で直面しがちな状況に応じた具体的なアプローチなど、わかりやすく解説します。 利用者への理解を深め、自信を持って日々のケアにあたるため、ぜひご参考にしてください。
目次
接し方の基本原則
認知症ケアの基本で大切なのは、利用者が抱える不安に寄り添い、人として尊重する姿勢です。この土台が信頼関係を築き、穏やかなケアを実現します。
尊厳の尊重
認知症になっても、その方がこれまで築いてきた人生やプライドは変わりません。記憶力が低下しても、羞恥心や感情は保たれています。子ども扱いする、失敗を責めるといった対応は自尊心を深く傷つけます。
一人の大人として敬意を払い「できないこと」ではなく「できること」に目を向け、本人の力を奪わない支援を心がけます。
笑顔とアイコンタクト
介護者の穏やかな表情や態度は、言葉以上に利用者の安心に繋がります。話す際は、相手の視野に正面から入り、名前を呼びかけましょう。
立ったまま見下ろすのではなく、しゃがむなどして目線の高さを合わせることが重要です。
「あなたを大切に思っています」というメッセージが伝わり、威圧感や不安を和らげられるでしょう。
ゆっくりわかりやすく話す
一度に多くの情報を伝えると、利用者は混乱してしまいます。話しかける際は、落ち着いたトーンでゆっくり、はっきりと話すことが大切です。
伝えたいことは「お風呂に入りましょう」「お茶を飲みましょう」のように、ひとつの文を短くして簡単な言葉で伝えます。
「はい」「いいえ」で答えられる質問も有効です。相手の反応を見ながらペースを合わせましょう。
傾聴と共感
話の内容が事実と違っていても、頭ごなしに否定するのは避けましょう。大切なのは、その言葉の裏にある不安や困っているという感情を受け止めることです。
「大変でしたね」と気持ちに寄り添い、「そうなんですね」と相槌を打つことで、利用者は「理解してもらえた」と安心します。
感謝や褒める言葉を伝えることも自己肯定感を高めます。
3つの「ない」
認知症サポーター養成講座を主催する認知症サポーターキャラバンは、認知症ケアの基本的な心得として、以下の3つの「ない」を提唱しています。- 驚かせない
- 急がせない
- 自尊心を傷つけない
後ろから急に声をかける、本人のペースを無視して急かす、失敗を責めるといった行動は相手を混乱させ、不安や不信感を増大させてしまいます。 穏やかな関係を築くための第一歩として、この3つの原則を常に心に留めてケアにあたりましょう。
参考:認知症サポーターキャラバン/ALSOK「認知症の方との接し方・対応「基本の3ない」と「10のポイント」」/なかまぁる「認知症の人にやってはいけないことは何?困ったときの対応方法と心構えを紹介」
状況別アプローチと注意点
基本原則を実践しても、実際の介護現場ではさまざまな状況に直面します。
それらは問題行動ではなく、利用者が何かを伝えようとしているサインのことが多いです。
ここでは、利用者の言動の背景にある気持ちを読み解き、適切に対応するためのアプローチを解説します。
意思疎通が難しい場合
言葉がうまく出てこない、話が通じにくいといった症状は、情報を処理する力が低下しているサインかもしれません。このような場合、早口で話したり一度に多くを伝えたりするのは禁物です。相手を混乱させるだけになるケースもあるため、笑顔や身振り手振りを交え、「はい」「いいえ」で答えられる質問にするなど、言葉以外の手段も活用しましょう。
「ゆっくりで大丈夫ですよ」という穏やかな態度が、本人の安心感に繋がります。
徘徊が見られる場合
徘徊は目的のない行動ではなく、不安や「~すべき」という思いの表れです。自宅にいても「家に帰らないと」と歩き回ろうとする姿を見たことのある職員は多いでしょう。
このときに、「ここがお家ですよ」と否定したり、無理に止めたりするのは逆効果です。
まずは「そうですね、帰りましょうか」と受け止め、一緒に帰る準備をするようにしながら話を聞きましょう。
そのうえで「お茶を一杯飲んでからにしませんか?」などと関心をそらす声掛けをしてみるのもひとつの方法です。
入浴や着替えを拒否する場合
入浴や着替えの拒否には、服を脱がされる羞恥心や浴室の寒さ、何をされるか分からない不安など、多くの理由が隠れています。「汚いから」と事実を伝えたり、「早くして」と急かしたりするのはプライドを傷つけ、拒否を強めます。
「一番風呂は気持ちいいですよ」と促したり「まず足だけ浸かってみませんか?」と段階的に誘ったりするなど、本人の気持ちを尊重した対応が必要です。
限られた時間で対応しなければならない訪問介護ですが、どうしても難しい場合は無理をせず、別のタイミングで対応することも考えましょう。
金銭管理が難しくなった場合
通帳や財布がなくなったと訴えたり、実際に金銭管理が難しくなったりすると、不安からくる「もの盗られ妄想」に発展する可能性があります。 矛先は一番身近にいる介護者に向きがちです。ここで「さっき自分でしまったでしょ」と事実を突きつけたり、犯人探しをしたりするのはタブーです。
本人の不安な気持ちに「それは心配ですね」と共感し、「一緒に探しましょう」と味方である姿勢を見せることが大切です。
利用者の安心のためにできること
認知症のある方への対応でより重要なのは、症状が起こりにくい環境を日頃から作ることです。
ここでは、利用者が自宅で安心して生活するための、予防的なアプローチを3つ紹介します。
視覚的なヒントを活用
言葉による指示よりも、視覚的な情報の方が利用者の理解を助けることがあります。例えば、トイレの扉に本人が分かる言葉で張り紙をしたり、タンスの引き出しに「ズボン」とラベルを貼ったりするといった工夫は有効な対応のひとつです。 こうした小さなヒントが本人の混乱を減らし、不安の軽減につながります。
危険を排除しておく
高齢者の転倒は骨折につながりやすく、入院や家族のもとへの引っ越しなどによる環境の激変は、認知症の症状を悪化させる大きな要因になります。訪問時、床に物やコードが散乱していないか、カーペットがめくれていないかなどを確認し、整理するだけでも効果的です。
また、洗剤や刃物などの危険な物が手の届く場所にないか、ご家族と一緒に確認することも大切です。
環境が大きく変わるようなアクションはしない
認知症の方は環境の変化に敏感で、テレビのリモコンのような物の配置や、ケアの手順が違うだけでも不安になります。訪問の際は、使った物を元に戻すなど「いつも通り」を意識しましょう。
そして、この「いつも通り」をチーム全員で実践し、一貫したケアを提供するためには、利用者に関する日々の細かな気づきや変化といった情報の共有が不可欠です。
まとめ
認知症ケアでは、利用者の尊厳を守ると同時に、職員自身が完璧を目指さず、一人で抱え込まない姿勢も大切です。
自身の対応がうまくいかずにストレスを感じてしまっては、良いケアの提供はできません。
質の高いケアとご自身のストレスマネジメントを両立する鍵は、チームでの「情報共有」にあります。
日々の気づきを円滑に共有できる「介護記録ソフト」は、利用者とあなた自身を守るチームケアを実現する有効なツールです。
Care-wingは、情報共有を円滑にし、利用者とあなた自身を守るチームケアを実現することができます。
チーム内の情報共有に興味のある方は、以下の資料をぜひチェックしてみてください。
【ライター】 織田さとる
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。
専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。
現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。
専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。
現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。