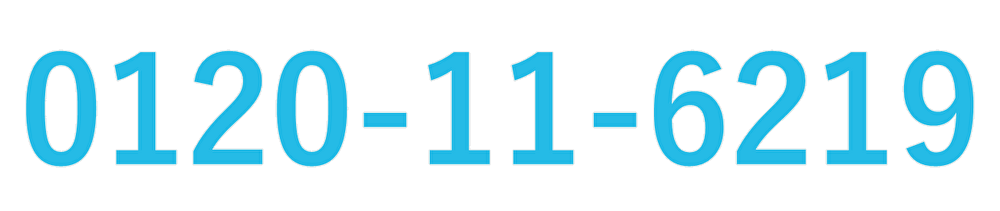-
公開日:
-
更新日:
【超高齢社会】介護・看護業界の現状にシステム化がなぜ必要?
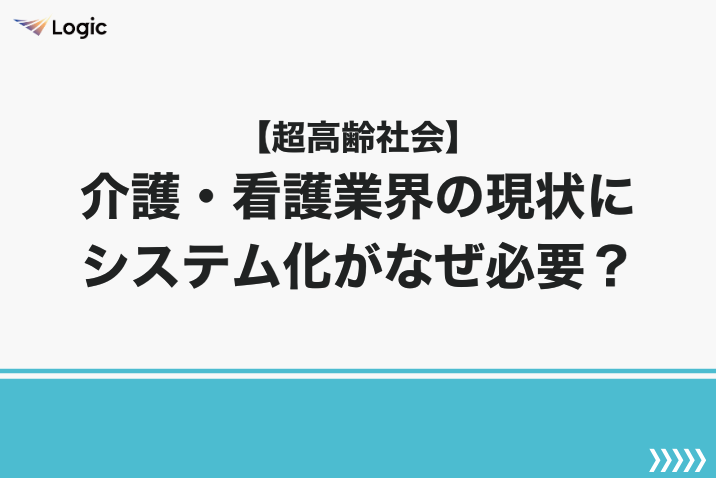
御存知の通り、日本はすでに超高齢社会といわれる時代に突入しています。
そして、超高齢社会といわれる現在においても、いまだ高齢者率の増加が進んでおり『国立社会保障・人口問題研究所』によると、2025年には全人口の高齢者が30%に達し、2026年には約40%になると予測されています。
この超高齢社会が進んでいけば、介護・看護業界の需要はさらに高まってくることでしょう。しかし現在の介護・看護業界にはさまざまな課題が存在しており、悩んでいる事業所もいるはずです。
それら課題を解決すると期待されているのが“システム化”ですが、これもまたあまり進んでいない現状があります。
そこで今回は、システム化の必要性を今一度把握するために、介護・看護業界の現状とシステム化を進めるべき理由やメリットを解説します。
介護・看護業界の抱えている問題とは
介護・看護業界が抱えている問題は大きく、誰しもが直面しうる身近な問題でもあります。どのような問題を抱えているかをご紹介します。
深刻な介護人材不足
高齢人口の急激な増加に比例して介護・看護を必要とする人口も増加。しかし少子化でもあるため日本の総人口は減少傾向にあり、介護・看護業界の人材不足は今後進んでいくことが予想されます。
また、2019年4月より働き方改革の関連法が施行されており、人手不足が問題となっている介護・看護業界も例外ではありません。
働き方改革とは、働く人が多様で柔軟性のある働き方を実現するために、有給休暇を確実に取得させなければいけなかったり、長時間労働に罰則付きの上限が規定されたりと、働く環境の見直す取り組みのことを指します。
働く環境が向上するような法案ですが、介護・看護業界の人手不足を解消することにはつながっていません。
このような社会の変化もあり、介護が必要であると認定されている“要介護者”を受け入れることができないことや、働いているスタッフに多くの負担がかかっていることなどが問題になっています。
個々の家庭への悪影響
これらの介護・看護業界の問題は個々の家庭にも大きな影響を及ぼしており、身近な問題となっている現状があります。
たとえば、高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や、介護が必要なのに適切な介護が受けられない“介護難民”、介護・看護によるストレスから発生する高齢者への虐待、高齢者の孤独死など。誰しもが直面してもおかしくないような、さまざまな問題が起こっています。
進まないICTの活用
ICTとは、和訳すると“情報通信技術”のことを指します。IT技術を活用してコミュニケーションをスムーズに行ったり、ペーパーレスで情報をまとめたりできるなど、業務や生活を豊かにするためのIT技術です。
全産業において人手不足を解消するために、生産性向上が期待できるICTの活用が推奨されていますが、教育分野などの分野では急速にICTの導入が進んでいる一方、介護・看護事業所ではICTの活用がいまだ進んでいない現状があります。
ICTの活用は経営陣が理解すればいいものではなく、介護・看護の現場で働く20代から70代、場合によっては80代までの幅広い年代のスタッフがICTを使いこなせるようになる必要があります。
もしもスタッフが理解できないような複雑なシステムを取り入れると、現場で混乱が起きてしまい、より業務を圧迫してしまう可能性があることが懸念されています。
また、ICTを導入するには、インターネット環境を整えたり、必要な機器の購入が必要だったりと、多くのコストがかかります。また、その維持にはランニングコストがかかるため、経営を圧迫する要因になりかねません。
ICT化を進めるために、国も補助金制度を出すなどして対策を進めていますが、現場では経営戦略と結びつくICT活用の考え方や教育の習得が進んでいないことが現状で、導入する準備も進んでいない状況です。
ICT活用で得られるメリット
ICT活用がいまだ進んでいない介護・看護業界ですが、実際にICTを導入するとどのようなメリットが得られるのかをご紹介します。
効率よく介護業務を行える
人材不足の問題を解消するためには、介護・看護業務を効率化することが有効です。
ICTを活用することによって、請求資料の作成やシフト管理、利用者情報の管理、スタッフ同士のスムーズな情報共有が従来よりも効率よく行うことができるようになるため、生産性が上がり、介護・看護にあたるスタッフの負担を軽減することができます。
また、ICTの活用は介護・看護の現場だけでなく、自治体や病院などの機関との連携もしやすくなります。
介護・看護業界では、事業所外にいる関係者とのやり取りも欠かせないため、関係者間でタイムリーに情報共有をすることは、職員の負担を減らすことにもつながり、利用者への最適なサービス提供にもつながります。早さだけではなく、正確性も高まるため、伝達ミスを防ぐといったことも可能です。
サービスの向上につながる
現場で働く介護・看護スタッフは、専門職ではなくてもできる業務も行っているケースがよくあります。それをICTを活用することで、見守りや書類作成の軽減が叶うため、本来行うべき専門職に専念することができます。
また、従来ではたくさんの書類を扱っていたデータもすべてパソコンやタブレット1つにまとめることができるため、身軽に利用者のケアを行うことができます。また、入力や操作の場所を選ばないため、移動時間やすき間時間を使って入力をすることが可能になります。
効率よく利用者のケアができるため、今までよりも利用者に寄り添ったケアが実現します。結果、介護・看護のサービスの質向上につながるということになります。
職場環境を改善できる
介護・看護業界では、仕事のやりがいを感じながら働く人がいる一方で、負担が大きい職場環境に不満を持って辞めていく人も少なくはありません。
ICTの活用を進めることでスタッフへの負担を減らすことが実現するため、長期的に介護・看護現場で働き続ける人材の確保ができ、働く方々が本来魅力を感じている業務に専念できるため、モチベーションアップにもつながると期待されています。
また、ICTを活用することで、スタッフの働き方に余裕が生まれ、有休が取れたり、残業を少なくできたりという働き方が実現します。業務時間を短くするためには、業務の効率化を行って生産性を上げることが不可欠であるため、ICTの活用は職場環境の改善に有効な手段といえます。
目指すのは介護・看護の現場に寄り添ったICT活用

介護・看護を必要とする人口が増え続けていることによって、現場で働く介護・看護スタッフの需給バランスが悪化していることから、一人ひとりのスタッフがとても貴重な人材です。
現場で働くスタッフが負担に感じていることや、求めている職場環境を知ることが介護・看護業界の抱える課題の解消につながるといえるでしょう。