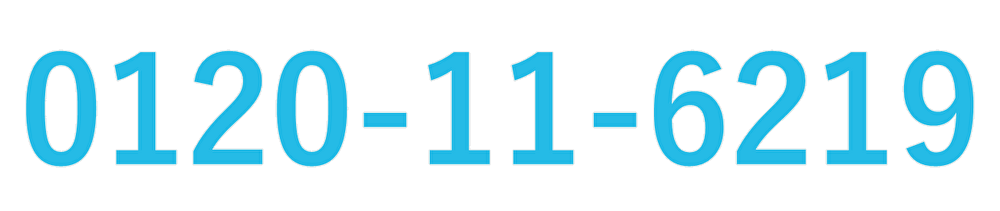-
公開日:
-
更新日:
訪問ヘルパー必見!道交法改正で厳しくなる自転車の交通ルールを解説
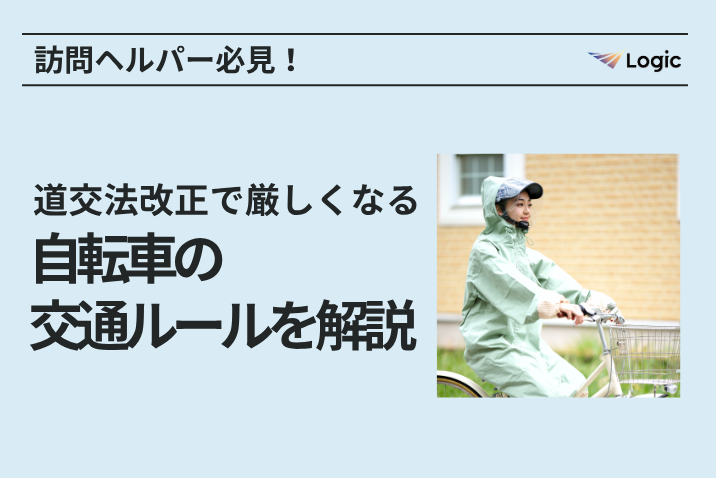
近年、自転車運転者の法令違反が原因で、歩行者や自転車運転者が死亡したり重傷を負う事故の発生が増えています。
交通ルールが遵守されていれば、悲惨な事故の防止につながる可能性が高いとも考えられており、自転車に関連する交通事故の増加や、危険な運転行為の抑制を目的として、道路交通法が改正されます。
道路交通法は2024年11月に改正されたばかりですが、2026年5月には自転車にも交通反則切符(青切符)の導入が決まっており、自転車に乗る機会の多い方は特に注意しておく必要があります。
今回は、そんな訪問介護の現場などの移動でよく使う「自転車の交通ルール」について、直近の改正内容を中心にご説明します。
目次
自転車の交通ルールのおさらい
自転車は、道路交通法上は「軽車両」に分類されます。
また、近年の改正で追加されたものは主に「危険行為」に該当します。
自転車における「危険行為」
自転車の「危険行為」とは、道路交通法で定められた特定の違反行為のことで、これらの行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられる対象となります。2024年11月1日に施行された改正道路交通法により、これまで14類型だった危険行為に「酒気帯び運転」と「携帯電話使用等(ながらスマホ)」が追加され、現在は16類型の危険行為が定められています。
危険行為(16類型)
道路交通法施行令 第41条の3(特定小型原動機付自転車危険行為等)
引用:警視庁「自転車運転者講習制度」「自転車の交通ルール」
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 優先道路通行車妨害等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害(道路交通法第37条)
- 環状交差点通行車妨害等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法63条の9第1項)
- 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
- 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5 (注記) )
- 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号又は道路交通法第117条の2の2第1項第8号)
近年追加された危険行為
2024年11月1日道路交通法の改正で、大きく2つの行為が危険行為として罰則の強化がされるようになりました。
①運転中のながらスマホ
以前より、「ながら運転」として、5万円以下の罰金が科せられていましたが、昨年罰則が強化されました。自転車を運転中に、スマホを手で持って通話することだけでなく、画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも罰則の対象になります。
ハンズフリー装置を併用する場合や停止中の操作は対象外とのことですので、スマホ操作や通話が必要な場合は、自転車を停止させたうえで行いましょう。
・違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
②酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。以前より飲酒して自転車を運転することは禁止されていましたが、これまでは「酒酔い運転」のみが処罰対象でした。
それが改正により、「酒気帯び運転」(一定量以上のアルコール保有状態での運転)も新たに罰則の対象となり、さらに、飲酒運転をする可能性のある人への酒類や自転車の提供(ほう助行為)も禁止されるようになりました。
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
【補足】
「酒気帯び運転」
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する行為のこと。
「酒酔い運転」
呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができない状況のこと。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、昨年の改正以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
「酒気帯び運転」
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいる状態で車両を運転する行為のこと。
「酒酔い運転」
呼気中のアルコール濃度とは関係なく、客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができない状況のこと。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、昨年の改正以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
参考:政府広報オンライン「自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設!」/警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」/大人の自動車保険「酒気帯び運転、酒酔い運転の違いとは?飲酒運転の基準や罰金を解説!」
危険行為をしてしまったら
自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関する一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命じます。(3時間/6,150円)また、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
【対象】
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。 ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。都内だけの取締り等に限りません。
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。 ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。都内だけの取締り等に限りません。
参考:警視庁「自転車運転者講習制度」
要注意!2026年に導入される自転車の「交通反則切符制度(青切符)」
次に、2026年4月に導入される、交通反則切符制度(青切符)について説明します。
今後の訪問時の自転車移動にも影響がある内容なので、しっかり罰則内容を理解しておきましょう。
交通反則切符制度とは
自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの (反則行為) について、一定期間内に郵便局 (簡易郵便局を含む。以下同じ) か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。また青切符とは、道路交通法などの交通法令に違反した運転者に対して、警察官が交付する書面(交通反則告知書)を指します。
今まで、自動車・原動機付自転車等にしかなかった制度ですが、2026年の改正以降は自転車でもこれまで警告や指導に留まっていた違反行為に対して、反則金が科せられるようになります。
一部引用:神奈川県警「交通反則通告制度とは」
交通反則切符制度(青切符)の対象となる違反行為と対象
主に以下の反則行為を交通事故の原因又は悪質性・危険性・迷惑性が高い違反として、交通反則切符の扱いになります。- 信号無視
- 指定場所一時不停止
- 通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
- 通行禁止違反
- 遮断踏切立入り
- 歩道における通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 携帯電話使用等
- 公安委員会遵守事項違反(傘差し) など
一部引用:神奈川県警「交通反則通告制度とは」
参考:警視庁「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」
訪問現場で更に注意したい自転車の反則行為
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)雨の日の訪問では移動中に傘をさすことももあるかもしれませんが、2026年の改定以降は交通反則扱いになるため、雨具(カッパ)・ポンチョなど早めに備えて、慣れておくことが必要でしょう。
・イヤホン・ヘッドフォンなどの使用により安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
急遽、移動しながら通話したい時もあるかもしれないですが、自転車に乗っているときは、イヤホン等は外しておきましょう。
参考:政府広報オンライン「自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設!」
まとめ
今回ご紹介した交通ルールは業務中だけではなく、私生活にも影響の多い改正になるかもしれないです。また、移動中に切符を切られたら、訪問の時間に間に合わないなんてことも起こりかねません。
反則行為とみなされないように、移動中の負担を軽減できるような対策を今から始めておくと良いでしょう。
Care-wingでは急なサービス内容の変更でも、変更内容をすぐに反映し確認することができたり、前回のサービスの内容を確認することができます。
移動に時間がとられても、訪問先についてからでも、スマホを見ればすぐ内容が確認できるので、移動中の電話を削減することにもつながります。 気になった方はお気軽にお問い合わせください。