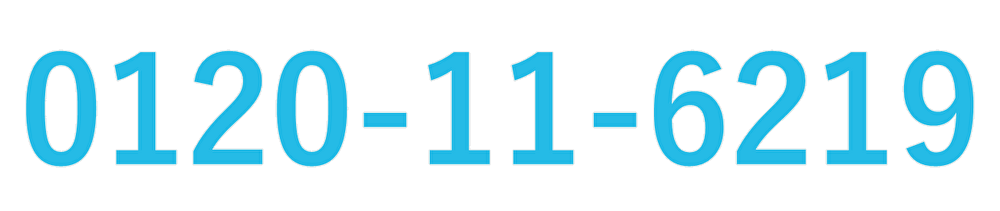-
公開日:
-
更新日:
訪問介護で不正請求を防ぐには?事例と防止策を紹介
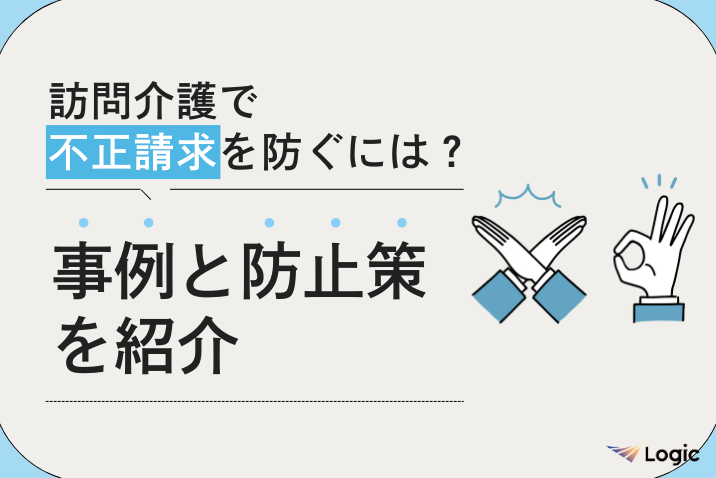
日本の高齢化が進む中、介護保険制度は高齢者の自立支援と生活の質を保つために不可欠な社会的インフラです。
特に訪問介護は、要介護者が住み慣れた地域や自宅で安心して暮らし続けるために必要不可欠といえるサービスです。
本格的に到来する超高齢化社会に対応するために安定した事業の継続が求められる訪問介護事業所ですが、時に事業の継続が困難になってしまう事態が生じます。それが「不正請求」です。
不正請求には、制度の複雑さや多忙な業務の中で、意図せずとも不正請求と指摘されたケースもあります。
そして不正請求と判断された事業所には、事業の継続を困難にさせる様々なペナルティが課されます。
今回は、不正請求の定義や具体例、発覚時の影響、そして防止策について解説します。
安定した訪問介護事業所の運営を継続するための参考にしていただけると幸いです。
介護保険制度における『不正請求』とは?
不正請求とは、介護保険法に基づくルールを逸脱し、提供していないサービスを「提供した」と偽って報酬を請求したり、加算や報酬算定の基準を満たさない状態で請求を行ったりすることを指します。悪意の有無にかかわらず、結果として介護保険制度の公正性と持続可能性を損ねる行為であり、重大な責任が問われます。
特に訪問介護は、比較的少人数で運営されている事業所が多く、記録管理や人員配置の変動に十分な対応が追いつかないまま請求業務が行われている現場も少なくありません。こうした背景もあり、全国でほぼ毎年、不正請求が監査や通報などで指摘されています。
過去に『不正請求』と判断された事例
例年、全国的に報道されたものだけでも約10件程度の不正請求がありますが、各自治体単位での不正請求はもっと多くの数に上ると見られます。では過去にあった訪問介護の不正請求事例を一部紹介します。
不正請求にあたるケース
- サービス実態がないまま報酬を請求した 住宅型有料老人ホームの入居者に対する夜間、早朝の訪問介護に関して、声掛け程度しか行っていないにもかかわらず、介護サービスを提供したとして介護給付費を請求し、受領した。
- 必要な計画を作成しなかった サービス提供に必要な介護計画書を作成しないままサービスを提供し続け、報酬を請求していた。
- 人員基準を満たさなかった 処遇改善に関連した加算の算定に必要な人員基準を満たさない状態であるにもかかわらず、同加算分の報酬を受領していた。
- スタッフ名の虚偽 実際には勤務していない職員がサービスを提供していたかのように記録し、介護報酬を請求していた。
- 無資格者を勤務させる 初任者研修以上の資格を持たない職員に訪問介護業務をさせていたが、有資格者が行ったかのように記録を捏造し請求していた。
- 「同一建物減算」を回避する工作 有料老人ホーム内にある訪問介護事業所を、実態のない場所にあると虚偽の申告をし、減算をせずに報酬を請求していた。
- 利用者の負担額を徴収しなかった サービスの利用時に利用者が負担するべき額を徴収せずに不当に割引を行った。
- 特定事業所加算の要件を満たす記録が残されていなかった 特定事業所加算の算定に必要な健康診断の記録や、個別の研修計画がない状態で同加算の報酬を受領していた。適切に研修等は行っていた可能性があるが不正請求と判断された。
以上のように、不正請求と指摘された事例は非常に多岐に渡ります。
明らかに不正請求であることを理解しておきながら行ったものも数多くありますが、気を付けたい事例としては不正請求にあたると認識しないままやってしまったケースです。
介護計画書が未策定だった場合
例えば、介護計画書が分かりやすいでしょう。介護計画書は訪問介護事業所が、利用者の何をどのように支援するのか、支援することで利用者のどのような姿を目指すのかを示すものです。 これらの策定は介護保険事業所である以上、必ず作成しなくてはならないものと義務付けられています。
介護計画書を未策定のままサービスを提供することは、いわば「利用者に対して何の課題分析や状態分析も行わないままサービスを提供している」ことと同じ意味になり、きわめて不適切かつ不確実なサービスを提供しているものとなります。
多忙な介護事業所の運営で、介護計画書の適切な作成や管理までなかなか手が回らないこともあるでしょう。
ですが未作成のままサービスを提供し続けることは、介護保険の制度上はルールに反する重大な違反行為なのです。さらには介護計画書を後回しにできること自体が介護計画書の活用を疎かにし、存在を軽んじていると言わざるを得ません。
いくら利用者にとって丁寧なサービスを提供していて、不正請求などする意図がなくとも、ルール上必要な書類を整備しなかったことでも不正請求と指摘されるケースがあることを事業者、管理者、スタッフ全員が認識しておくことが大切です。
不正請求が発覚した場合の処分とは
訪問介護事業所をはじめ、不正請求が発覚した場合は以下のペナルティが課されます。悪質と見なされた不正請求には事業の存続が困難になる場合もあります。
不正請求と判断された介護報酬に上乗せして返金
不正請求と判断された場合に必ず課されるペナルティが、不正請求に相当する介護報酬や加算額の返金です。ただ全額を返金すればよいのではなく、不正請求の総額に4割を乗じた額を返金する必要があります。つまり100万円が返金対象ならば140万円の返金を命じられるのです。長期に渡り不正請求を行ってきた事業所や、規模の大きな法人では数千万単位の返金となることもあります。
運営の一部制限
不正請求と判断された場合の違反措置として、一定期間の営業停止や新規利用者の受け入れ停止を命じられることがあります。書類が整備されていなかった等に起因する不正請求に多く見られる傾向です。
介護保険事業所の指定取り消し
最も重いペナルティが介護事業所の指定取り消しです。故意に記録を捏造する、人員体制を偽る、不正請求の規模が大きいなどの悪質な不正請求に対しては、次回の指定更新を行わない措置や、指定の更新を待たずに事業の停止命令が出されることもあります。
不正請求を防止するために気を付けたいポイント
不正請求は意図的に行ったものではなくとも該当してしまうリスクがあります。もし不正請求と指摘されてしまった場合でも、よほど悪質でない限りは返金や一部制限のペナルティに留まり、事業の停止とまではいかない場合もあるでしょう。
しかし、不正請求を行ったという事実は変わりません。これは利用者やその家族、近隣住民、居宅のケアマネや職員の信頼を大きく損なう事態です。 結果的に事業所の評判が大きく下がり、信頼の回復には長い時間を要しますし、利用を避けられる、職員が働くモチベーションがなくなり退職してしまうなど円滑な運営を困難にさせてしまうことは確実です。
そこで、故意ではない不正請求を防ぐために押さえておきたいポイントを以下に紹介します。
人員基準を満たさなくなったらすぐに報告する
訪問介護事業所は利用者の数に応じてサービス提供責任者を適切に配置しなければならない運営基準が定められています。また、特定事業所加算には職員数に対して介護福祉士の資格保持者の割合が定められています。
人員の入れ替わりが多い介護業界で、この割合は変動しやすいものです。もし利用者40人に対し1人のサ責が配置できない場合は、訪問介護事業所を運営するための基準を満たしていないことになり、そのまま営業を続けることは規約違反となります。
また特定事業所加算の場合は介護福祉士の割合が足りないまま営業を続け、従来の加算の報酬を得ることは虚偽の請求と見なされて不正請求の対象となります。
そこで大切なことが、毎月の人員体制をチェックするシステムを構築し、もし配置基準を満たせなくなった場合にすぐに自治体の介護保険課に報告することです。 サ責の人数が足りない場合はいつ頃に人員基準を満たせそうかなどの猶予措置が設けられることがありますし、特定事業所加算においては基準を満たせない時点で加算分を請求しなければ不正請求にはあたりません。
売り上げが下がってしまうことは、経営の難しい訪問介護には痛手ですが、不正請求のペナルティに比べれば、はるかに良いでしょう。迅速かつ誠実な対応が最も大切なのです。
利用実績は毎日記録する
訪問介護員をはじめサ責、管理者も忙しく動き回ることの多い訪問介護では、利用の実績や記録の確認業務は後ろに回されがちです。そして、訪問介護は利用者都合のキャンセルや、職員の急な休み等で代替職員がいないことによるキャンセルもしばしば見られます。これらを月の終わりに一気に実績登録していくとなると、チェック漏れが発生しやすくなり、場合によっては利用実績がないのに利用したとして請求してしまう事態にも発展します。これは故意ではなくとも不正請求となりえます。
こうした事態を防ぐためにも、利用実績は毎日確実に記録しておくことが重要です。時間が足りないのであれば、業務のシステムを変更してでも重要度の高い業務に位置付ける、介護記録ソフトで効率化するなどの改革が必要です。
運営や加算に関する記録は確実に残す
訪問介護事業所は、ケアマネや相談支援員がプランニングした計画書に沿って訪問介護計画書を作成し、利用者の望む生活のために必要な目標を訪問介護という手段でアプローチする仕事です。このプロセスには計画に沿って訪問介護を提供しているという証拠を残すことが適切な運営をしている唯一の証明手段です。訪問介護計画書を作成していないのは論外ですが、計画に沿ったケアを提供していない場合も、不適切な運営として監査等で指摘を受ける場合があります。
これを防止するためには、毎回の記録を確実に残すという理解だけではなく、運営や加算に関連した記録を残すという意識が大切です。 事業所内で、必ず残さなくてはいけない記録を確認、共有し、必要な記録を必要な分だけ残す習慣をつけていくと、不正請求を防止するだけでなく質の高い記録にブラッシュアップしていくことにもつながります。
記録には時間がかかりますし、紙のサービス実施記録票では情報の共有が困難な場合が多々ありますので、介護記録ソフトで効率化を図ることで記録業務の省力化および記録確認業務の効率化に大きく寄与します。
まとめ
訪問介護事業所の不正請求は、悪質でなくても人員体制が足りなくなった、書類の作成を後回しにしてしまった等で意図せず発生してしまうリスクがあります。 不正請求を防止することは、事業所の適切な運営および信頼感のある事業所であることをアピールするためにも重要な意味を持ちます。
不正請求につながりかねない事象を改めて洗い出し、必要であれば介護記録ソフトの導入や活用方法の見直しを行い安心できる訪問介護事業所づくりを目指しましょう。
弊社の介護記録ソフトCare-wing(ケアウイング)では、各サービス毎の指示が、ソフト内で記録と紐づく形で残るため、不正な請求の防止に役立ちます。
「不正請求をしない」ではなく「不正請求にならない」仕組みづくりこそが長く信頼される訪問介護事業所への第一歩です。
<ライター> 寺田 英史
20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。
初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。
20年以上の介護業界経験を持つ介護の専門家。短期入所、訪問介護を経て、現在は介護保険外サービスも運営。
初任者研修、実務者研修の講師も務める。現場目線の分かりやすい記事で、介護職や介護現場の課題解決に貢献。