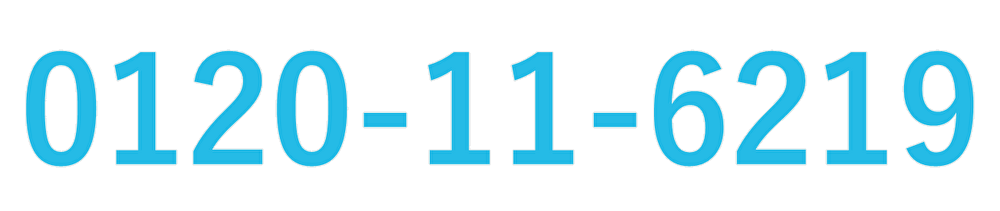-
公開日:
-
更新日:
サ責さん必見!サービス担当者会議の流れと進め方のポイント
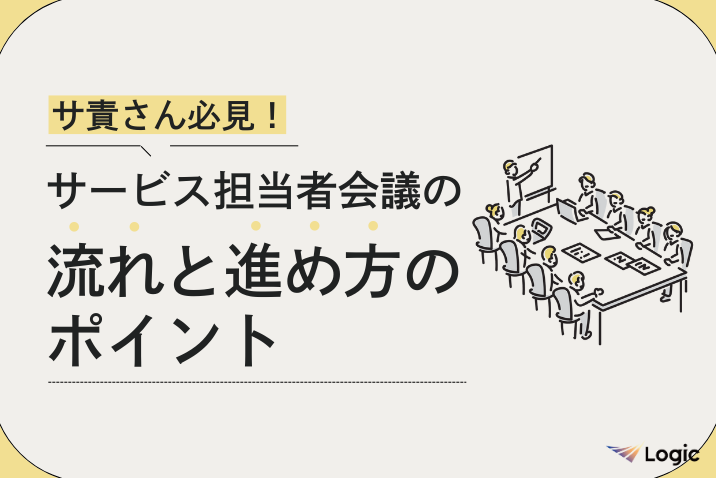
「担当者会議に出席するけど、何を話せばいいんだろう」
訪問介護の現場で、そう不安に感じたことはありませんか?
担当者会議は、利用者や家族、ケアマネジャーやその他の専門職が集い、最適なケアの方針を話し合う場です。
訪問介護員には、日頃のケアで得た利用者の情報を的確に伝えるという大切な役割があります。
本記事では、担当者会議の目的といった基本から当日の流れ、そして会議で自信を持って発言するためのコツまで分かりやすく解説します。 チームの一員としてケアの質を高めるために、ぜひご参考にしてください。
目次
担当者会議とは
担当者会議は、ケアマネジャーが主催し、利用者のケア方針を決める会議です。訪問介護員もチームの一員として参加し、より良いケアプランを作るために情報共有や意見交換をおこないます。
介護のプロとして関わる上で、その目的や意義を正しく理解しておくことが大切です。
担当者会議の目的
一番の目的は、利用者や家族の意向を再確認し、それをもとに最適なケアプランを作成することです。ケアマネジャーが作った原案に対し、訪問介護員や看護師、リハビリ専門職などがそれぞれの視点で意見を出し合います。
これにより、関係者全員が「チーム」として同じ目標を共有し、一貫性のある質の高いサービスを提供できるようになるのです。
担当者会議のメンバー
会議はケアマネジャーが主催し、中心となるのは利用者とその家族です。その他に参加する主な職種は以下の通りです。
- ケアマネジャー
- サービス提供責任者
- 訪問介護員
- 訪問看護師
- デイサービスの相談員
- ショートステイの相談員
- 福祉用具専門相談員
このように、ケアに直接関わる専門職がそれぞれの立場から参加します。 やむを得ない理由で欠席する場合は、事前に文書で意見を提出することもあります。 その内容は会議でしっかり共有され、議事録にも残されます。
開催時期と頻度
担当者会議は、ケアプランの作成や更新、要介護認定の更新や区分変更があった際に開催されます。また、入院や怪我などで心身の状態や生活環境に大きな変化があった場合、プランの見直しが必要なときにも随時開催されます。
定期的な見直しだけでなく、予期せぬ状況の変化にチームで迅速に対応するために、必要に応じて集まります。
訪問介護事業所としての役割
訪問介護員は、利用者の生活に最も密着している専門職です。そのため、日々のケアで気づいた心身の変化や、ご本人が口に出さないニーズなどをチームに伝える重要な役割を担います。- 固いものが食べづらくなってきた
- トイレまでの動線に手すりがあった方が良い箇所がある
- 2週間ほど前からヘルパーが帰る前に急に寂しそうになることが続いている
このように、他の専門職が知り得ない「在宅でのリアルな情報」の提供が、より良いケアプラン作成につながります。
また、会議で決まったことは事業所に持ち帰り、ヘルパー全員で共有することも大切な仕事です。
なぜ担当者会議をスムーズに進めることが重要なのか?
担当者会議は、利用者を中心としたチームケアの出発点となる場です。
それぞれの専門職が持つ情報を共有し「どうすれば利用者が望む生活を送れるか」という共通の目標設定をおこないます。
そして、その目標達成のために最適な支援方針の調整を議論するのが、この会議の役割です。
会議のスムーズな進行が、ケアの質に大きく左右します。
スムーズな担当者会議がもたらすメリット
1.利用者、家族の意向が確認できる
会議がスムーズに進み、和やかな雰囲気であるほど、利用者は「こうしてほしい」という本音を話しやすくなります。専門職に囲まれている環境では、利用者や家族は緊張して気後れしてしまいがちです。
だからこそ、専門職が意識して発言しやすい雰囲気を作ることが大切になります。 専門家が一方的に話すのではなく、本人が安心して発言できる機会も大切です。そこから私たちが気づけなかった課題や要望が見つかり、より利用者の希望に沿ったケアの実現につながります。
2.他職種と情報共有できる
訪問介護や訪問看護、デイサービスなど、普段は別々に動いている専門職が一堂に会する貴重な機会、それが担当者会議です。顔を合わせて直接情報交換をすることで互いの人柄も理解でき、チームとしての連携が深まります。
それぞれの専門的な視点からの情報が合わさることで、利用者をより多角的に理解できるようになります。
3.質の高いケアプランが作成できる
利用者の本当の意向がわかり、多職種からの専門的な情報がそろうことで、はじめて質の高いケアプランが作成できます。会議での活発な意見交換を通じて、ケアプランの原案がより利用者の現状に合った、実現可能な計画の作成へつながります。
会議の流れ・スムーズに進めるコツ
担当者会議を成功させるには、当日の進行だけでなく、事前準備と事後の情報共有も大切です。
ここでは、訪問介護事業所のスタッフとして参加する会議のステップを、「事前準備」「会議当日」「事後処理」の3つに分け、会議を円滑に進めるコツを解説します。
1.事前準備
まずヘルパーは、担当利用者の日々の記録を確認し、気になる変化や伝えるべきことをメモにまとめておきます。 サービス提供責任者は、各ヘルパーからの情報を集約し、事業所としての報告内容を整理します。このとき、手書きの記録ではなく介護ソフトがあれば、全スタッフの記録をリアルタイムで集約できるため、作業が効率化され、より精度の高い情報整理が可能になります。
2.会議当日
会議はケアマネジャーが進行しますが、正しい情報提供はもちろんのこと、参加者の一人として和やかな雰囲気作りも心がけましょう。 他の専門職の意見にも耳を傾け、チームの一員として会議の運営に協力します。発言する際は、パソコンやタブレットを活用できると、過去の記録をその場で確認しながら説明したり、質問に的確に答えたりでき、発言のヌケモレや勘違いを防げます。
3.事後処理
会議後、ケアマネジャーから共有された議事録と新しいケアプランをもとに、事業所内で情報共有をおこないます。サービス提供責任者は決定事項をヘルパー全員に周知し、訪問介護計画書を更新します。このときも、介護ソフトを使えば更新された計画や重要事項をデータで一斉に共有でき、伝達もれを防げるでしょう。
ヘルパーは、更新された計画内容を各自の持つ端末から確認し、翌日からのケアに反映させます。この情報共有の速さと正確さが、チーム全体のケアの質を保つことにつながります。
このように、日常の記録や担当者会議の準備や情報共有の際には、介護ソフトを活用すると業務の効率化につながります。
Care-wingなら、リアルタイムで情報共有でき、過去の記録の検索も簡単な操作で可能です。
興味のある方は、ぜひ資料をチェックしてみてください。
訪問介護事業所が算定できる担当者会議に関連する加算
訪問介護事業所が算定する加算の中で、担当者会議への出席が要件になっているものはありません。
よく間違えられやすい加算に、質の高いサービスを提供する事業所を評価する「特定事業所加算」があります。
この加算は、介護福祉士の割合や重度者の受け入れといった要件を満たすことで算定できる加算で、算定要件のひとつに「定期的な会議の開催」という項目があります。
しかし、ここで言う会議はケアマネジャーが主催するサービス担当者会議のことではなく、サービス提供責任者が主催する、訪問介護事業所内部の会議です。 事業所に所属するヘルパー全員の参加が義務付けられていますが、一堂に会する必要はなく、複数回に分けて開催することも認められています。混同されやすいので注意が必要です。
参考:厚労省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問5(箇条書きの3つめ)」/東京都福祉保健局「特定事業所加算の算定要件の留意事項」-「会議の定期的開催」/カイポケ「2024年度改定対応】訪問介護の特定事業所加算とは?」
まとめ
本記事では、担当者会議の目的から具体的な進め方のコツまでを解説しました。利用者を中心とした質の高いチームケアを実現するために、担当者会議は欠かせないプロセスです。
そして、会議を成功させる鍵は、日々の記録に基づいた正確な情報共有にあります。
介護ソフト「Care-wing」を活用すれば、日々の記録から会議の準備、決定事項の共有までがスムーズになり、ヘルパーやサービス提供責任者の負担を軽減できます。
より質の高いケアと、スタッフが働きやすい環境の実現を目指している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
【ライター】 織田さとる
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。
専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。
現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。
介護業界で20年以上の実務経験を持つケアマネライター。
専門学校卒業後、特別養護老人ホームで介護福祉士、ケアマネジャー、生活相談員として勤務。
現在も施設で働きながら、介護・福祉分野の記事を執筆している。
保有資格:ケアマネジャー、介護福祉士、社会福祉士、公認心理師など。